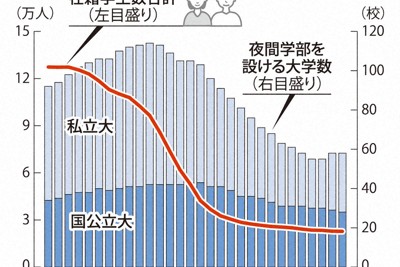4本の脚と座る座面、そしてもたれるための背。肘は、あるものも、ないものも。椅子を構成する要素はごくわずかだが、素材や仕上げの選択、意匠の工夫などによって、これまでに数えきれぬほどデザインされてきた。年月を経るほどに愛され続ける名作も多い。それでもなお、これまでにない視点でデザインされた椅子に出合うと、心が躍る。家具メーカーの飛驒産業の「HIHI」と「DADA」が、まさにそうだ。
この2脚、一見とても似ているのだが、HIHIは左右対称にデザインされているのに対して、DADAは違う。肘の部分が途中で途切れていたり、座面の枠が後ろにはみ出していたりとアシンメトリーなのだ。椅子は左右対称につくることで構造的に安定し、私たちの体重を支える。ではDADAが座れないのかというとそんなことはなくて、むしろ座り心地はいい。なんとも不思議な椅子である。
デザインしたのは、デザイナーの三澤遥さん。東京・麻布台ヒルズにエルメスがオープンした際の広告プロモーション、上野動物園の知られざる魅力をウェブサイトなどで見せるプロジェクト、国立科学博物館の標本資料を全国に貸し出すための移動展示キットの開発など、仕事は多岐にわたる。

製作した飛驒産業は、社名の通り岐阜県の飛驒高山にある家具メーカーで、今年設立105年という歴史を持つ。同社が三澤さんに椅子のデザインを依頼した際のリクエストは、「名作椅子をつくってほしい」という、シンプルかつ遠大なもの。三澤さんは大学で椅子の研究者に教わった経験はあるが、家具のデザイナーではない。「家具デザイナーではないからこそ、何が生まれるか期待があった」と飛驒産業デザイン室の小平美緒さんは言う。
三澤さんは何もアイデアがない状態でまず飛驒高山の山を訪れ、木が育つ環境を見た。さらに工場やショールームに足を運び、この会社と山の関係の深さや、技術の蓄積を体感した。多くの家具を見たなかで一番印象に残ったのが、日本のプロダクトデザインの第一人者である柳宗理氏がデザインした「ヤナギチェア」の復刻版。優美な曲線を描く椅子で、曲木(まげき)という、蒸気で蒸して柔らかくした木を型枠に入れて成型する加工技術を用いている。

飛驒産業の曲木の技術は国内屈指といわれ、厚さ50ミリ、幅200ミリという尋常ではないサイズのナラ材も曲げるほど。機械を駆使しつつも、曲げに要する時間の見極めなど、最終的には職人の腕がものを言う。製作現場を目の当たりにした三澤さんは、学生時代に製作した椅子を思い出した。それは、アシンメトリーなデザインの1脚。高い技術を持つ飛驒産業の職人と一緒に挑戦することで、ユニークなアシンメトリーの椅子をつくれるのではないか。こうして、アシンメトリーな椅子と、似ているけれどもシンメトリーな椅子の2脚をつくることが決まった。
そこからは、三澤さんが針金や3Dプリンターを用いてたくさんの模型をつくり、それらを基に飛驒産業が試作する工程が続いた。

椅子のセオリーにとらわれずデザインする三澤さんと、デザインの意図を損なうことなく、道具としての強度と座りやすさは譲らない飛驒産業。互いの立場と役割を尊重しながら、両者ともに妥協せず、せめぎ合い、検討を重ねた。目立たないところに部材を加えて補強してあったりと、その跡は随所に見られる。
商品化に向けて何より大変だったのは、座面と脚、背と肘などの接合部分。三澤さんがこだわったのは「丸い棒同士がちょんと付いているくらいの、さりげなさ」だ。「椅子だけど、椅子らしからぬたたずまい」をつくりたかったと言う。当然、堅牢(けんろう)さや安定性からは離れていく。椅子のあるべき姿からまたもや逸脱する提案で、アシンメトリーよりも難易度は高かった。

通常ならダボやホゾを使って部材を接合し、強度も高められるところだが、接合面積が小さく難しい。そこで片方の部材を削り、丸棒が交わる見えない箇所にビスを入れる手法を編み出して試作した。商品化には日本産業規格(JIS)が定める強度試験に通らねばならないが、1回目は通過ならず。ビスの種類を変更して強度を上げ、さらにオリジナルの金具を仕込むことにより、2回目の試験でクリアした。
試験の結果を待つ間、三澤さんも小平さんも「我が子を見守るような気持ち」だったという。「森で木の育つ様子を見ていたこともあって、椅子は人より長生きするかもしれない、生き物のようなプロダクトだと思えてきた」と三澤さんは言う。
当初の希望だった曲木加工も、調達などの事情で丸棒状の木を接いで成型する方式に変更になっている。だがこれはサンプルを見た三澤さんが「接ぎ木部分のジグザグ模様がチャーミング」と、むしろ愛着を持った。

HIHIもDADAも、国産のブナ材を用いている。飛驒産業の創業の背景には、地元のブナ材の活用という目的があった。1980年代からは輸入材が増え、一時期は原材料のすべてが輸入材に。輸入材は大径木が多く、木目が均一なのに対し、国産材は細く、節も目立つ。それでも日本の山の未来も見据えて、再び国産材を原料にし始めたのは21世紀に入ってからのこと。
野趣に富む節を魅力ととらえた家具シリーズを発表するなど、国産材を積極的に使用している。現在は約20%の国産材を使った家具の売り上げを30年に30%に上げることを目指すが、国産材を使っているというだけでは消費者に響かない。それを可能にするのが「デザインの力」なのだと小平さんは話す。
ライター 鈴木里子
吉川秀樹撮影
[NIKKEI The STYLE 2025年7月27日付]
 【関連記事】
【関連記事】
- ・エルメス主催の馬術大会はパリの風物詩 馬具へのこだわりに宿る精神
- ・ロエベが手仕事にこだわる理由 クラフトの動画には「若い世代が注目」
■取材の裏話や未公開写真をご紹介するニューズレター「NIKKEI The STYLE 豊かな週末を探して」も配信しています。登録は次のURLからhttps://regist.nikkei.com/ds/setup/briefing.do?me=S004
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。