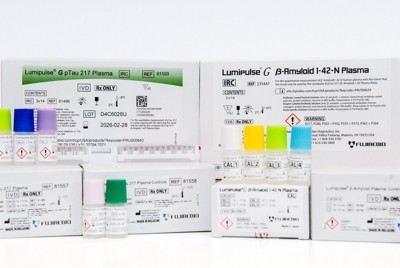冷えと乾燥が気になるこの季節、心と体を潤す一杯はぜひ紅茶で――。
午後のアフタヌーンティーを楽しむ「ヌン活」や国産の「和紅茶」などの広がりで、新たな「紅茶ブーム」が訪れている。
それに加えて、生理学的な分野でも紅茶の機能に注目が集まっている。視線の先にあるのは「紅茶ポリフェノール」だ。
腸内環境を整えたりウイルスを不活化させたりする作用が顕著なことが近年の研究で分かり、世界的にもその健康機能が見直されている。おいしいだけではない紅茶の特徴とは。
緑茶よりウイルスを不活化
「日本紅茶協会」が定めた「紅茶の日」(11月1日)に先立つ10月30日、ヘルスケアに関する調査や情報発信を行う「ウェルネス総合研究所」が、紅茶ポリフェノールに関するセミナーを東京都内で開いた。
「喉が乾燥したら、紅茶を飲む。一杯で終わりではなく、飲み続けるのが効果的」
そう呼びかけたのは、登壇者で、茶の研究を長年手がけてきた静岡県立大の中山勉客員教授だ。
ポリフェノールはココアや豆類、ベリー類など多くの食材に含まれる天然化合物の総称で、8000種類以上が存在するといわれている。色味や風味のもととなり、種類によって機能は異なる。

そのうち紅茶ポリフェノールは、もとは緑茶やウーロン茶と同じチャの葉を紅茶へと加工する過程で生成される。主な種類に赤みや渋みのもととなるテアフラビン類とテアルビジン類がある。
「緑茶も紅茶もウイルスを不活化する作用がありますが、紅茶ポリフェノールのうちのテアフラビン類の方が効果が高いという研究結果があります」(中山さん)
この10年、世界中で紅茶研究の論文が増え、その機能が解明されつつあるという。コロナウイルスやインフルエンザウイルスの表面のリン脂質膜にテアフラビン類は強く吸着し、宿主に感染しにくくするというのが中山さんの研究の一つだ。
また、もう1人の登壇者で甲南女子大の川畑球一准教授(食品機能学)によると、ポリフェノール類は構造が大きく、飲んでも小腸でほとんど吸収されず最終的に大腸に流れていく。
そのため、約100兆個存在するといわれる腸内細菌にさまざまな働きかけをし、腸内環境が整う効果があるという。
つまり、風邪などの感染症リスクが高まったり、食べ過ぎに飲み過ぎと食生活が乱れやすくなったりする冬は特に、紅茶が健康維持に役立つ可能性があるということだ。
おすすめは濃くて渋いストレート
セミナー終了後、中山さんに効果的な飲み方を聞いた。
「濃くて渋いのがいいんです」。これは、成分が多いということらしい。
ただし、牛乳を加えるとポリフェノールと吸着して抗ウイルス効果が減るのでストレートがおすすめだ。お供のお菓子やケーキの食べ過ぎにも注意したい。【山崎明子】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。